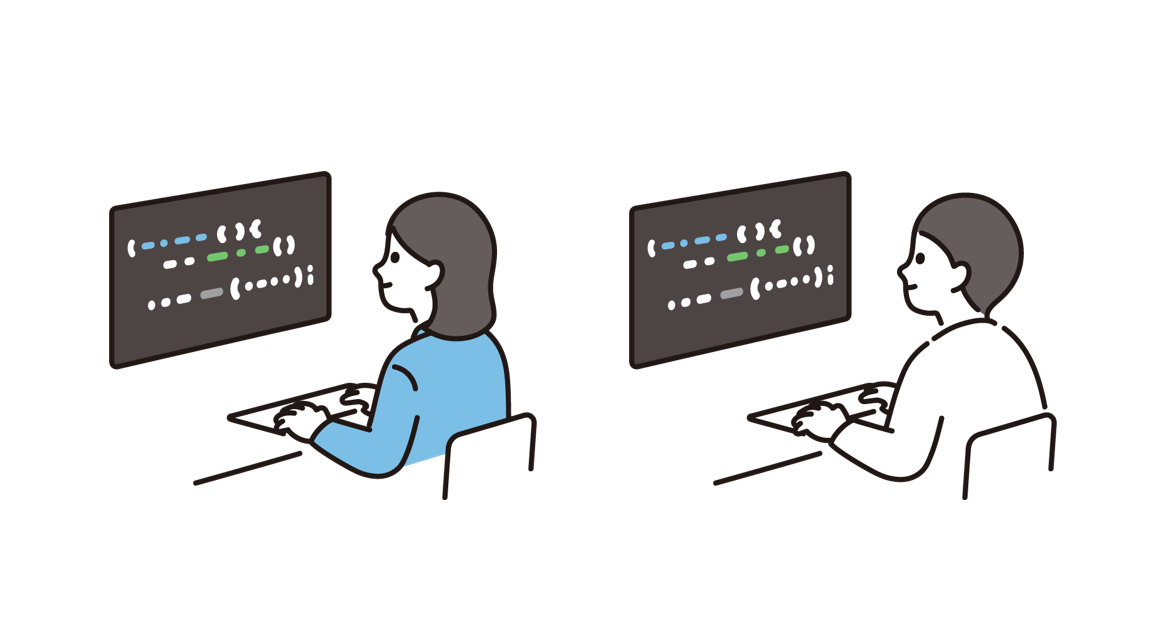目次
はじめに
こんにちは! 2025年度新卒エンジニアの佐伯です! 株式会社リクルートの新卒エンジニアは、部署配属が行われる前に約4ヶ月間のBootCampと呼ばれる新卒研修に参加します。 今回は2025年度の研修の内容と、実際に受講した立場から学びになったことなど紹介させていただきます。
研修の概要
研修は、配属後速やかに業務に取り組める状態になることを目指し 、以下3点を目的として行われます。
- 様々な技術領域の講座を受け、興味関心を広げながら、エンジニアとして成長する土台を獲得すること
- 配属後、現場で求められる「仕事への取り組みスタンス」をつかむこと
- 気軽に相談できる仲間を作ること
これらの目的の通り、配属先に関わる技術以外にも幅広いエンジニアリング技術を体系的に学ぶほか、事業理解やロジカルシンキング・活躍されている先輩方のナレッジ共有などヒューマンスキルについて学ぶ講義も用意されていました。 エンジニアリング研修については特に、入社前に行われたスキルアセスメントテストの結果を踏まえ、受講者の習熟度・理解度に合わせたクラス分けが行われていたため、アプリケーション開発の経験がない人でもレベルに合わせた講義を受けられる形となっていました。
また、各研修では講義でのゴールを明示的に共有いただくと共に「将来必要となった時のインデックスを貼り地図を作ることが重要」ということをお話がありました。 これは、学び続ける必要のあるエンジニアが技術をキャッチアップし続けることにも通じると感じており、社会人としてのキャリアの早い段階でこの考えに触れられたのは、非常によい経験でした。
加えて、技術だけではなく事業理解・事業開発についての講義も多く、リクルートのビジネスモデルのひとつである「リボンモデル」に始まり、事業の中心が紙媒体からインターネットへと 変化した歴史、事業をどのように成長させてきたかを学ぶ講義もあります。 幅広く学ぶことで、ただ開発するだけではない、事業へ影響を与えていくエンジニアとして成長できる講座となっていました。
研修内容・資料
実際の研修の内容と、資料の一部を公開いたします。
ぜひ、参考になさってください。
| No | 講座名 | 資料公開 | 資料リンク | 備考 |
| 1 | 導入研修 | ✕ | — | |
| 2 | PdMケイパビリティ研修 | ✕ | — | |
| 3 | 配属前導入研修 | ✕ | — | |
| 4 | エンジニアの心構え | ◯ | ソフトウェアエンジニアとしての姿勢と心構え | 「生成AIとの向き合い方」パートを追加 |
| 5 | テスト駆動開発 | ◯ | 見てわかるテスト駆動開発 | |
| 6 | 攻撃と防御で実践するプロダクトセキュリティ演習 | ◯ | 攻撃と防御で実践するプロダクトセキュリティ演習~導入パート~ | |
| 7 | ブラウザ | ◯ | Browser | |
| 8 | Webアクセシビリティ入門 | ◯ | Webアクセシビリティ入門2025 | |
| 9 | 事業価値とエンジニアリング | ◯ | 事業価値と Engineering 2025版 | |
| 10 | 制約理論(TOC)入門 | ◯ | 制約理論(ToC)入門 | |
| 11 | TPS入門 | ◯ | トヨタ生産方式(TPS)入門 | |
| 12 | モダンフロントエンド開発研修(旧NextJS) | ◯ | モダンフロントエンド 開発研修 | 初開講 |
| 13 | 実践データベース設計 | ◯ | 実践データベース設計 ①データベース設計概論 | リファクタリング課題や設計課題など、インタラクティブ要素を盛り込む |
| 14 | アプリ開発概論 | ◯ | モバイルアプリ研修 | 資料公開は今年度から |
| 15 | セキュリティ研修 | ✕ | — | |
| 16 | つくって納得、つかって実感! 大規模言語モデルことはじめ | ◯ | つくって納得、つかって実感! 大規模言語モデルことはじめ | 初開講 |
| 17 | JavaScript | ◯ | JavaScript 研修 | |
| 18 | TypeScript | ◯ | TypeScript入門 | |
| 19 | 実践アプリケーション設計 ①データモデルとドメインモデル | ◯ | 実践アプリケーション設計 ①データモデルとドメインモデル | リファクタリング課題や設計課題など、インタラクティブ要素を盛り込む |
| 20 | 実践アプリケーション設計 ②トランザクションスクリプトへの対応 | ◯ | 実践アプリケーション設計 ②トランザクションスクリプトへの対応 | 同上 |
| 21 | 実践アプリケーション設計 ③ドメイン駆動設計 | ◯ | 実践アプリケーション設計 ③ドメイン駆動設計 | 同上 |
| 22 | スピードハッカソン | ✕ | — | |
| 23 | パフォーマンス系演習 | ✕ | — | |
| 24 | 全社検索研修 | ✕ | — |
印象に残った講座3選
エンジニアの心構え
全ての研修の中で一番初めに受講した講座になります。 この講座は当社の技術顧問である 和田卓人(@t_wada)さんが担当してくださっており、学び続ける必要のあるエンジニアがどうやって学び続けるのかというお話をしていただきました。
この講座の目的としては「特定の技術を学ぶ」ではなく「技術の学び方を学ぶ」と設定されていました。 技術の流れも早く、生成AIによる変化も多い激動の時代において、各所で活躍されているエンジニアの学び方を聞く中で自分はどう動いていくか考えるタイミングになりました。
「これからエンジニアとして活躍するんだ」という期待に胸が膨らむと同時に、その道を進む上での覚悟が定まり、背筋が伸びるのを感じました。 全ての研修の最初にこの講義があったからこそ、続く研修にも全力で取り組めたのだと思います。
今後エンジニアを続ける中で、定期的にスライドを見返し、いつでもこの気持ちに立ち返れるようにしたいです。
攻撃と防御で実践するプロダクトセキュリティ演習
この研修では、実際に攻撃を受けることの多い脆弱性を対象として、アプリケーションに存在する脆弱性を利用して「フラグ」を取得するCTF(Capture The Flag)形式の攻撃演習と、その脆弱性を修正する防御演習を体験しました。
課題アプリケーション自体もさまざまな言語で作られており、様々な言語や脆弱性に触れる中で、セキュリティを常に意識する重要性を再認識しました。 また、演習はチームに分かれて攻撃や防御に成功すると加算されるポイントを競い合うゲーム形式で行われたため、楽しみつつ、同期の強みや戦略の立て方に触れながら、実践的なスキルを学ぶことができました。
演習後の解説パートも非常に充実しており、具体的な対策方法を深く理解できました。今後、多くの方に利用していただくプロダクト開発に関わる中で、セキュリティ意識を常に高く持ち続けなければならないと、改めて身が引き締まる思いでした。
実践アプリケーション設計・実践データベース設計
この研修では、他の研修と並行して取り組む必要のある事前課題が出されました。 事前課題のお題自体は、最低要件はあるもののゴールの定めかたは各自に委ねられており、これまでの講義内容を活かしたいという思いから、TDD(テスト駆動開発)やDDD(ドメイン駆動設計)といった、これまで学んだ知識を実践しようと試みました。 しかし、通常の講義もあり他の課題もある限られた時間の中で挑戦的に取り組んだため、計画通りに進めることの難しさに直面し、最終的には「提出できる形」にすることを優先しました。 この経験から、限られたリソースの中で現実的なゴールを設定し、着実に成果を出すための見積もりと計画の重要性を痛感しました。
研修当日は「データベース設計からアプリケーション実装までの広範囲なナレッジを体系理解し俯瞰できるようになる」というゴールに向けて、座学に加えリファクタリング演習に取り組みました。 リファクタリング課題では、座学で学んだ項目を実践的に活用する方法を学べたことに加えて、今後チームで取り組んだりAIと協業したりする中で、他者のコードを正確に理解し、より良いものへと改善していく「コード読解力」を磨く絶好の機会となりました。
終わりに
これらの研修で得られたものは、講義で学んだ知識やスキルだけではありません。 何よりも印象的だったのは、同期の仲の良さと、共に学び合う文化です。
各講義ではSlack上で実況するチャンネルがあり、リアルタイムで質問や感想を共有していました。 さらに、ある講義で紹介された今取り組んでいることや考えていることを投稿していくWorking Out Loudを取り入れ、各自が日々の学びや課題を "times"というメンバーごとの日報や、考えていることを気軽に記載できるオープンチャンネルで発信していました。 誰かがわからないことを投稿すれば、すぐに誰かが助けてくれる環境ができており、お互いに助け合い、学びながら取り組む様子が多く見られました!
お互いに高め合い、支え合うこの環境があったからこそ、困難な課題も乗り越えることができたのだと感じています。
講師の方々が用意してくださった充実した研修はもちろんのこと、切磋琢磨し合える同期に恵まれたおかげで、技術的なスキルと社会人としての心構えの両面で、大きく成長する ことができました。 そして何より、かけがえのない仲間との絆を育むことができた、非常に密度の濃い日々でした。